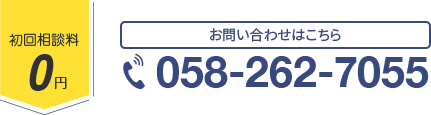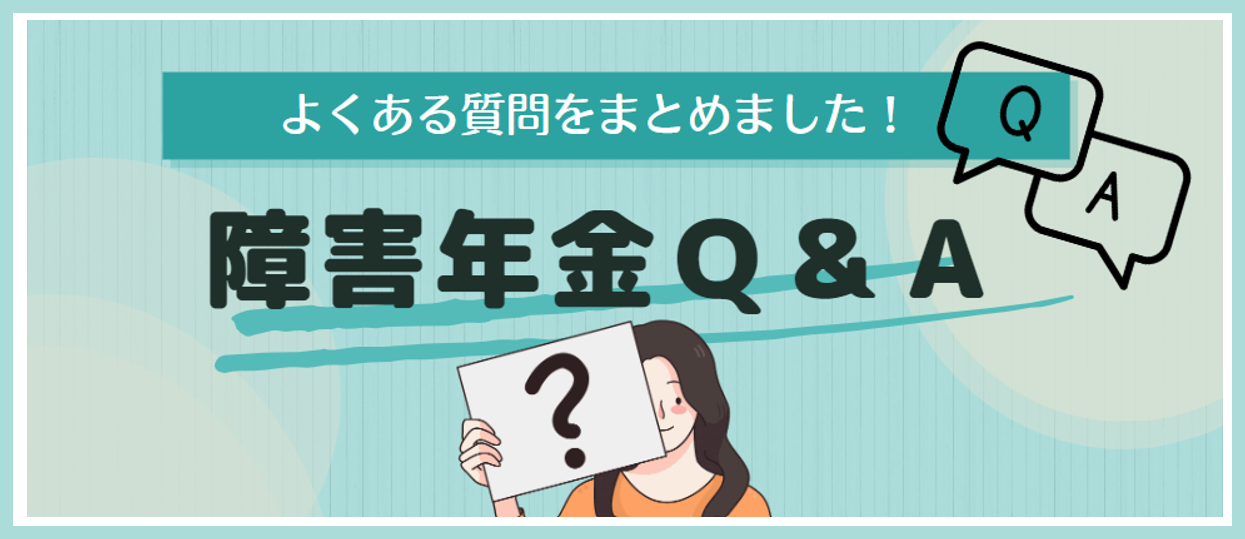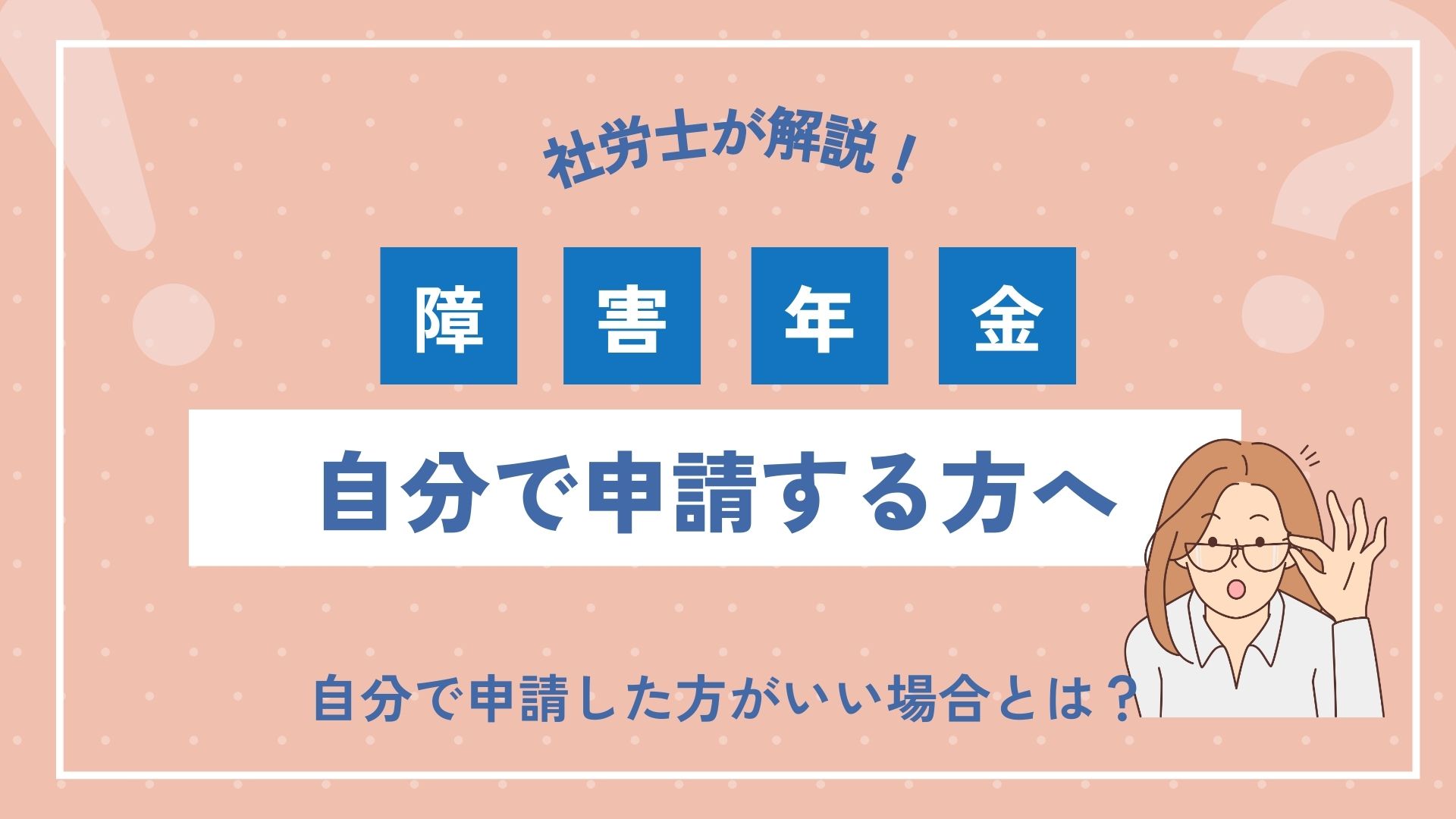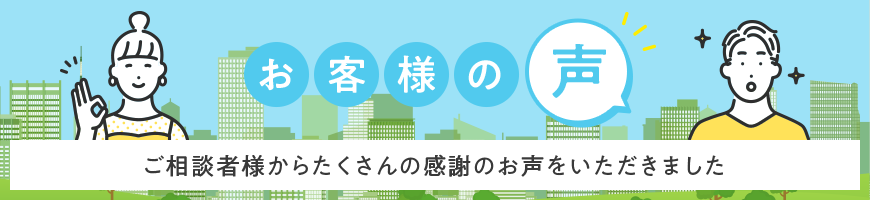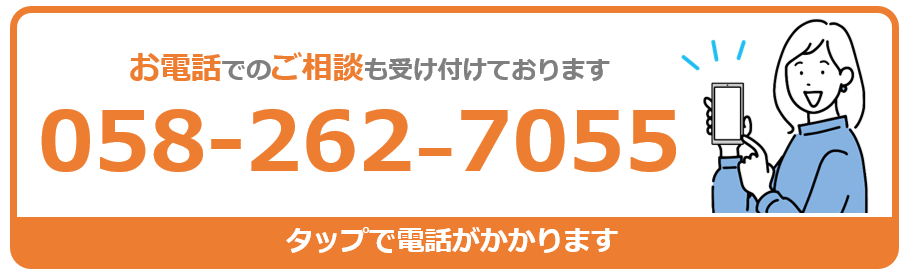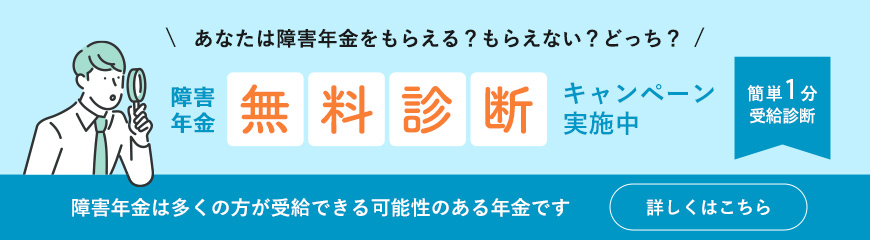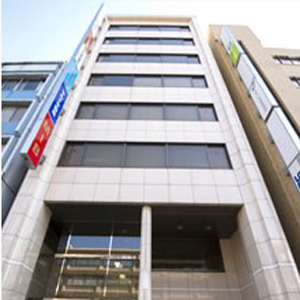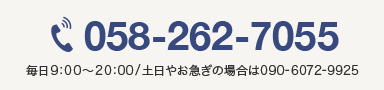障害年金受給のメリット・デメリットを社労士が解説!要件を満たしていても要注意!?
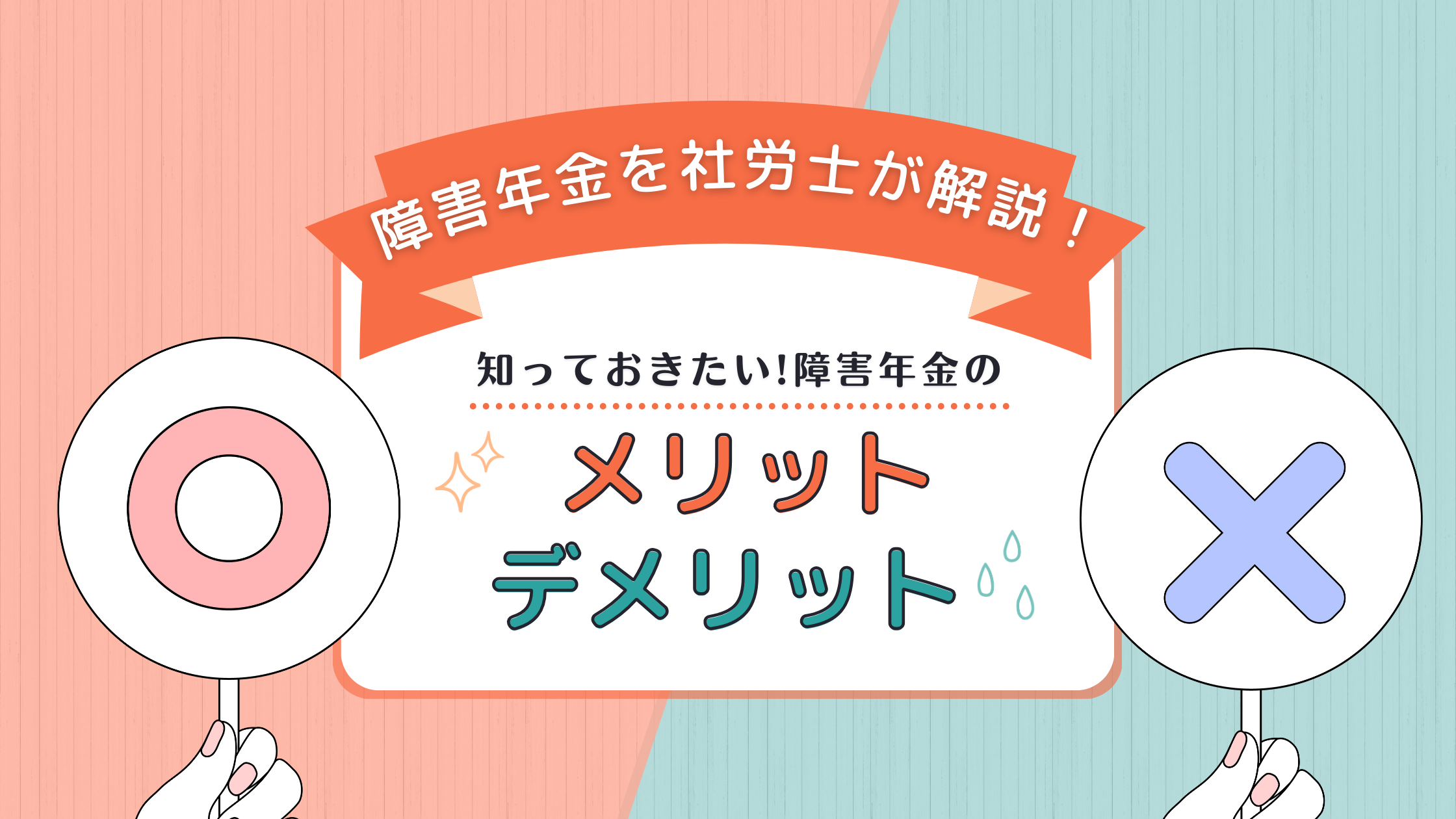
障害年金は、心身の障害を負ってしまった場合など、経済的あるいは心理的に非常に大きな支えになります。もし、不幸にも病気や怪我をしてしまい、障害年金を受給できる要件を満たしているのであればきちんと請求するべきだと思います。
ただし、障害年金もわずかでありますがデメリットもあります。受給してから、しまったと思わないために、事前に確認しておくことが大事です。
そこで、考えられる障害年金をもらうデメリットについて説明します。また、ページ後半ではメリットについてもご紹介します。デメリットと併せてご確認ください。
障害年金をもらうデメリット
1.法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる。
障害年金1級または2級に認定された場合、国民年金保険料の支払いの免除を受けることが可能です。
これを「法定免除」といいます。法定免除を受けると、国民年金の保険料を納める必要はなくなりますが、その代わり法定免除の期間の老齢基礎年金は、保険料を全額納付していた場合に比べて2分の1で計算されます。
その分だけ65歳以降にもらえる老齢基礎年金の金額は減額されます。
ただし、将来的に障害年金が支給停止される場合に備えて老齢年金の額が減らないように法定免除期間中であっても保険料を納める手続きをすることもできます。
そうすれば老齢基礎年金は減額されません。
2.生活保護との調整がある。
障害年金と生活保護は併給されません。
基本的に障害年金を受給した金額分だけ生活保護が減額されます。
両者のメリットとデメリットを事前に検討して決めて下さい。
3.傷病手当金との調整がある。
傷病手当金は健康保険に加入している方が私傷病や病気で仕事ができなくなり収入がなくなった場合、健康保険からだいたい給料の3分の2が健康保険から支給される制度です。
傷病手当金はもらい始めてから1年6か月まで支給されますので、通常はまず傷病手当金を受給し、その後仕事に復帰できない場合障害年金に移行することが一般的ですが、例えば障害年金を訴求して請求する場合、障害年金の受給期間と傷病手当金の受給期間が重複すると障害年金の受給額だけ傷病手当の金額が調整されます。
なお、両者の傷病名が異なる場合は調整されません。
4.死亡一時金・寡婦年金がもらえない。
死亡一時金は国民年金の加入者が年金を受給することなく死亡した場合、その家族に支給される一時金です。
そのため本人が障害年金を受給していれば死亡一時金は支給されません。
ただし、死亡一時金は最大でも32万円ほどなので、障害年金を受給して6か月ほどで、障害年金のほうが金額的に上回ると思います。
寡婦年金は保険料を納めた期間が10年以上ある国民年金の夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳まで支給されます。
夫が会社員だった場合は寡婦年金の対象外なので検討する必要はありません。
5.社会保険の扶養から外れる可能性がある。
障害年金の額が180万円を超える場合、または障害年金と他の収入を合わせて180万円を超える場合は健康保険の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険及び国民年金に加入することとなります。
ただ、障害年金の最低保証は約50,000円なので、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入する費用を上回っていると言えます。
以上のように、障害年金もわずかながらいくつかのデメリットも存在します。
しかし、前もってそれらを検討しておくことによって回避することができます。
障害年金をもらうメリット
1.経済的な不安が軽減される
経済面を心配される方は多くいらっしゃるかと思います。障害が原因で働けなくなれば、収入が減少し生活を営むのが難しくなります。
こういった場合、障害年金を受給することで、①家計を安定させる、②治療に専念する、ことが可能です。経済面の不安やストレスを軽減し、病状の回復に専念できる環境を整えましょう。
2.年金の使い道は自由
障害年金の大きな特徴として、使い道が限定されていないことがあげられます。治療費以外に、生活費や貯蓄に回すことも可能です。
これに対して、生活保護を受給した際は、所有できる資産に制限がかかります。住宅や自動車の購入に生活保護費を充てることは原則できないことになっています。
3.就労していても受け取れることがある・周囲に知られない
障害年金は、働きながらでも受給が可能です。また、職場や親戚等の周囲の人にも知られることはありません。
ただし、働き方によっては障害年金を受給できないケースもあります。現在の就労実態で障害年金を受給できるか判断がつかない場合は、ぜひご相談ください。
4.障害年金に税金はかからない
障害年金は所得とみなされないので、非課税所得に分類されます。そのため、税金を支払う必要がなく、確定申告等において障害年金の受給額を申告する必要はありません。
これに対して、老齢年金は課税所得のため、年金で得た収入に応じて税金を納める必要があります。
5.国民年金保険料の支払いが法定免除になる
障害年金の1級又は2級に該当し、法定免除を受けると障害年金受給中の国民年金保険料の納付が全額免除されます。
この場合、法定免除となった期間は国民年金保険料の納付はありませんが、国が半分支払ったとして将来の老齢基礎年金の額が計算されますので、将来受け取る老齢基礎年金にも半額は反映されます。
法定免除を受けて「現在」の負担を軽減するか、法定免除を受けずに国民年金保険料を納付して「老後」に備えるかは、受給者自身で選択できます。
障害年金を受給する際は、デメリットも把握しておく必要があるでしょう。
しかし、デメリット以上にメリットが大きいため、この制度を有効活用することをお勧めいたします。